蒸し暑い毎日が続いています。今日は、午前中に買い物に行く予定でしたが、強い雨が降ってきてしまったので、読書の続きをすることにしました。
二 『楚辞』[天問]篇
中国の神話は、『楚辞』の[天問]によくまとめられています。『楚辞』は、古く南方の揚子江流域に栄えた楚の祭祀的歌謡、巫祝者の文学であり、[天問]は、作者の屈原が、古代神話が描かれた壁画に沿って、天に問う形で展開されます。
作者の屈原は、諸国の巫の伝承が流れ込む楚の地で、前3世紀初め頃に王族の1人として巫祝を率いていたと思われます。伝承が薄れ、すでに崩壊に近い危機的な情況のなかで、巫祝者たちが、自らの存在の根拠となる神話的古伝承に対する根本的な懐疑を、哀惜の念を以てもらしたものであろう、と白川氏は述べています。
[天問]では、壁面に画かれた事実が次々に問われていきます。天地未発のはじめを誰が今に伝えたのか、天の形、大陸の地勢、月日のめぐりや列星のつらなりについて。独り神の女神女岐、人を作った女神女媧、洪水説話の聖人鯀・禹、洪水神であり破壊神である共工(康回)、崑崙山に住む百神…
のちに夏王朝の反逆者となる太陽を射落とす弓の名手羿が画かれ、続いて夏・殷・周王朝の物語、さらには春秋戦国の英賢のことにまで問いが及びます。作者は国の運命を思いながら、「帰らんとして何をか憂ふ」と嘆きます。
後漢末の王逸の注によると、その壁画は、楚の先王の廟および公卿の祠堂に描かれていたもので、上下数層、あるいは左右にも区画されたものと推測できます。壁画が時系列の絵巻物式ではないこと、[天問]の次序に前後するところがあることからも、神話自体が、楚の歴史と連なるところのない分列的な形のままであったことがわかります。すなわち、[天問]篇の神話は、C類型にふさわしい形態で述べられている、と白川氏は結論づけています。
殷の紂王といえば、藤崎竜『封神演義』
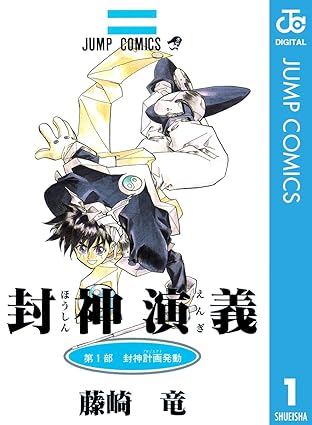
↑ 封神演義 1 (ジャンプコミックスDIGITAL) Kindle版
今回の部分では、古代の三王朝の物語が出てきましたが、やはり殷の紂王といえば、イメージするのは藤崎竜さんの漫画『封神演義』です。
私が中学生ぐらいのときに連載していて、コミックスを友達から借りて読んでいました。その友達(女の子)は、穏やかで優しい子だったのですが、今思うと、なぜこんな漫画を好んで読んでいたのでしょうか…子どもが読むには、グロすぎます。「酒池肉林」という言葉は、この漫画で覚えましたが、妲己の残酷で卑劣でエロスを振りまくイメージも強烈に焼き付きました。
漫画『封神演義』の主人公太公望。伝説では、武王による殷周の革命をたすけ、釣り糸を垂れながら、東海より西方の聖王を求めて旅したということですが、確かに、太公望の使う武器は釣り竿がモチーフになっていたような気がします。
太公望呂尚の名前は[天問]にも見られます。帝に犠牲をささげたのち、山東の斉に封ぜられたとのことで、「釣り糸を垂れて~」の部分については白川さんは否定しています。
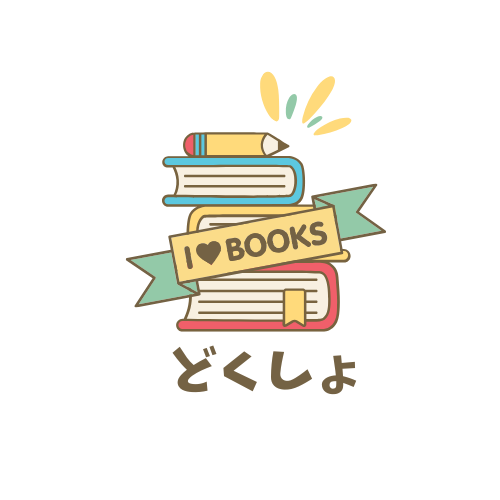


コメント